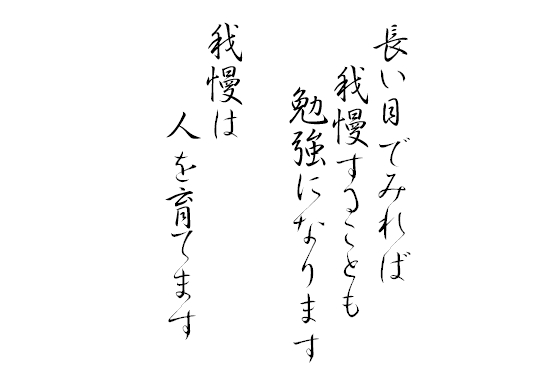3月ですね。
異名だと「弥生」という事になります。
草木がいよいよ生い茂るとの意味で、「いやおい」という言葉が
もとになった言葉だと聞きます
多くの植物が芽を出し、成長し始める時期なので、気持ちも温かくなったり
しますね(*^^*)
3月というとお雛さまを思い浮かべます
ひなだん飾りの順番のアプリを開発した方が有名になってましたが
私も、よく知らないので、ここで少し教養のためにも
列記したいと思います
参考
1段目 内裏雛(だいりびな)お殿さまとお雛さま
向かって左が「男びな」右が「女びな」*昔は、左側(向かって右)上手(かみて)、右側(向かって左)下手(しもて)といって、
位の高い人ほど上手(かみて)に
座っていたそうです。
2段目 三人官女 お殿様、お姫様の世話をする人
3段目 五人ばやし 太鼓や笛をもって、能を演奏する人
4段目 随身(ずいしん) お内裏様の家来で、向かって左が右大臣、右が左大臣。左大臣の方が、右大臣よりも、位が上です。
5段目 三仕丁(さんじちょう) 宮中で、雑用する人たち
6段目 たんすや鏡台、茶道具
7段目 かごや御所車
ひな遊びは、昔、貴族で行われていた「流しびな」の風習と
貴族と子供たちの間で行われていた人形遊びが結びついたもの。
やがて、豪華になって、江戸時代には今の行事になっていったようですね
ひな人形は、『15体』が、飾られるのですね
今回は、ひなまつりの料理も調べます

- ちらし寿司
- 白酒
- ひなあられ
- ひしもち
- ハマグリのおすいもの
桃の節句と言われるひな祭り、モモは、病気や災いを払う植物と言われてきたようですね
女の子の孫がいるワタシは、すくすく育って欲しいと思い、ひな祭りを楽しみたいと思います
日本の文化には、大切な行事が含まれていますね
ひなまつりの歴史についてまとめてみたいと思います
ひなまつりは
日本の伝統的なお祭りで、毎年3月3日に行われます。ひなまつりは、女の子の健やかな成長を願う節句であり、また、日本の伝統的な文化や美しさを讃える行事でもあります。
ひなまつりの起源は、平安時代にさかのぼります。当時、桃の節句と呼ばれる行事があり、桃の花や桃の枝を飾って女の子の健康を祈りました。その後、江戸時代に入り、ひなまつりという名称がつけられ、今日のようなお雛様や雛祭りの慣習が定着しました。
ひなまつりには、お雛様と呼ばれる人形を飾ることが伝統的な慣習となっています。お雛様は、天皇や皇后、侍女や従者などの役割を持つ人形で、数段に並べられた段飾りに飾られます。また、白酒や菱餅、菱のあんこなどの特別な食べ物も用意され、親しい人々と一緒に楽しまれます。
現代のひなまつりは
日本の伝統的な行事として親しまれています。子供たちは、家族や友人と一緒にお雛様を飾ったり、特別な食べ物を楽しんだりします。また、多くの地域で、ひなまつりのパレードやお祭りが開催され、大勢の人々が集まって楽しんでいます。
ひな人形は、お雛様とも呼ばれ、日本のひな祭りで用いられる人形のことです。お雛様は、平安時代から日本で伝統的に飾られており、5段のお雛様を中心に、多くの小物が飾りつけられます。
お雛様の5段にそれぞれ飾られる人形
上段:雛席
上段には、天皇と皇后が座る雛席が飾られます。天皇と皇后は、お雛様の中で最も大切な役割を担っています。彼らは、日本の伝統的な宮廷文化に基づいて、重要な役割を持つ人物とされています。
二段目:三人官女
二段目には、三人官女と呼ばれる、宮廷での音楽や踊りを担当した女性たちが飾られます。三人官女は、祝い事や儀式で活躍した女性たちを表しています。
三段目:五人囃子
三段目には、五人囃子と呼ばれる、笛や太鼓を演奏する音楽家たちが飾られます。五人囃子は、宮廷や公家の間で親しまれた楽団を表しています。
四段目:宮中の従者
四段目には、宮中で働く従者たちが飾られます。従者たちは、日常生活で宮廷内で重要な役割を担っていた人々を表しています。
五段目:武家の家臣
五段目には、武家の家臣が飾られます。武家の家臣たちは、戦国時代や江戸時代の武士の服装を模したもので、武士道精神や武士の美学を表現しています。
これらの役割を持つひな人形は、お祝いの席に飾られ、家族や友人たちと一緒に楽しまれます。また、日本の伝統的な文化を伝える重要な役割を担っています。